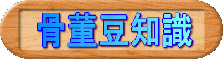
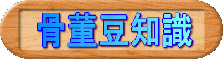
| 焼製が不十分な為、器の表面に寛入が入ってしまったもの。器としての評価は下がる。 |
| 商売人がよく使う言葉で人にあまり知られていない器のことをいう。専門書や雑誌などに掲載されていないものをいう場合もある。マニアの間ではうぶものの方が好まれることもある。 |
| 釉薬をかけて本焼した焼き物に色絵の具で絵付けをし、再び六〜七百度の低温で絵を焼き付ける技法 |
| 金直し、金繕いともいう。直し(なおし)の方法のひとつで、器の割れや欠損部をパテ等で修正した上から金箔を貼って磨く技法。同様に銀継ぎの技法もある。この直しは鑑賞の対象でもある。 |
| 焼き物の品質の善し悪しは、上手・中手・下手でランク付けされる。発色や雑な絵柄のものが下手となり、品質が悪いと判断される。ただし、古い時代の焼き物の場合は下手であっても高い価値をもつ事がある。 |
| 下手(げて)とは逆に、一級品であること。発色が優れていたり、手の込んだ絵付けがなされている。ものが上手にランク付けされる。 |
| 金(銀)継ぎともいう。焼き物のヒビや損傷を膝やパテで埋め、金や銀の粉をかけて補修すること。 |
| 素地を素焼きする代わりに陰干しし、その後釉薬をかけて焼く技法。初期伊万里によく使われている技法でもある。 |
| 焼き物の表面から素地までヒビが入ってしまっているもののこと。貫入(かんにゅう)よりもヒビが深い状態で、骨董としての価値も下がる。 |
| 中国の明の時代に始まり、伊万里焼でもよく用いられた絵柄。器の見込みに大きく花や鳥、人物を描き、八等分した周辺部に吉祥分や草花を描く分様。全体では大輪の芙蓉が咲いてるように見えることからこの名が付いた。 |
| 焼物を重ね焼きする時に、上下の器物のくっつき防止の為陶土を小さく団子状にしたものを挟んでおく。「目跡」とは、焼き上がった器物の畳つきと見込みの間にみられる、この陶土の痕跡のこと。 |
| 陶器や磁器などの真偽や善し悪しが見分けられる人物 |
| 器の緑に切り込みを入れ、花弁のような形にしたもののこと。5弁のものを特に梅花という。 |